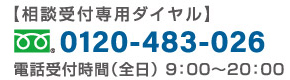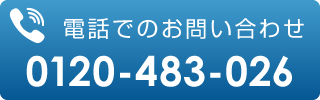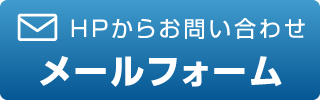事例4
会社員のXさんは、69歳。
Xさんには、66歳の妻Bさんのほかに、Bさんとの間に授かった長女Cがいます。
長女Cは、東京の会社に就職して以来、40年以上も、XとBが暮らしている大阪に帰ってきません。Xが病気で入院した時も帰ってきませんでした。
そうかと思えば、毎日のように、Bに金の無心の電話をしてきて、Bから多額のお金を受け取っています。
Xさんは、自分の死後のことを考えるようになりました。
Xさんには、預金は葬儀をあげるくらいしかなく、あとは、Bさんと一緒に暮らしている自宅があるだけです。
検討
1 遺言を作っていない場合にどうなるか?
相続人はBとC。相続分は2分の1ずつ。
XとBが住んでいた自宅のみが遺産。
遺言を作っていない場合には、自宅を売却することになる可能性が大きい。
2 遺言を作るだけでは不十分
では、「自宅をBに」という遺言を作れば、Bは自宅を守ることができるのか?
答えは,NO!
Cには,遺留分がある。
3 遺留分ってなに?
遺留分は,遺言によっても奪えない権利
故人の遺志を尊重するために,遺言という制度を設ける一方で,
残された相続人のために,最低限相続できる財産を保障
(遺留分権者と遺留分割合)
- ① 遺留分があるのは,配偶者,子ども,直系尊属だけ。兄弟姉妹はなし。
- ② 遺留分割合①:直系尊属のみが相続人の場合は,相続分の3分の1
- ③ 遺留分割合②:配偶者,子どもが相続人の場合は,相続分の2分の1
4 例えば…
先ほどの事例で,自宅の価値が2000万円だった場合,
子Cの遺留分は,2000万円×2分の1×2分の1=500万円。
妻Bは,Cから請求があれば,500万円の支払義務を負う。
お金がなくて支払えない場合は,結局,自宅を売却することに。
5 対策
単に遺言を作ればよいわけではない。
遺留分を考えて,遺言を作る必要がある。
遺留分侵害の遺言を作るのであれば,その対策が必要。
例えば,Bを受取人とする生命保険に加入しておく。
X死亡時にBが保険金を受け取り,そこからCに支払いをする。
そうすることで自宅を守る!!

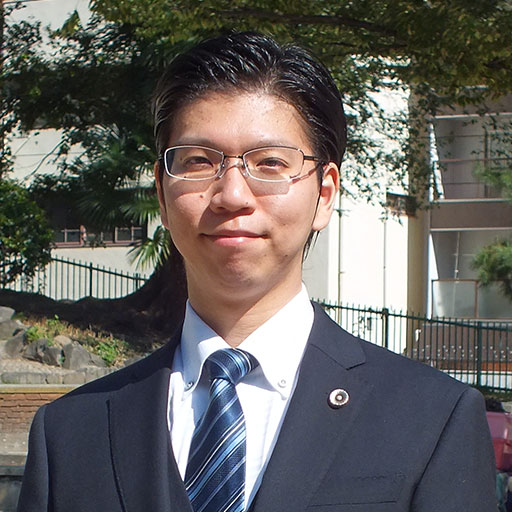
当事務所は、企業法務、交通事故、相続、男女問題、借金問題、刑事事件など、身近な法律問題から専門的なご相談まで幅広く対応しております。
豊富な経験と実績を持つ弁護士が、ご相談者様一人ひとりのお悩みに真摯に寄り添い、最善の解決策を導き出すために誠心誠意サポートいたします。
主な対応エリアは 大阪市、東大阪市、八尾市、柏原市、奈良県 ですが、全国各地のお客様から多数のご依頼を頂戴しております。
エリア外にお住まいの方や営業所がある場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
法律問題は、一人で抱え込まずに専門家へ相談することが解決への第一歩です。お電話またはお問い合わせフォームより、いつでもお問い合わせください。